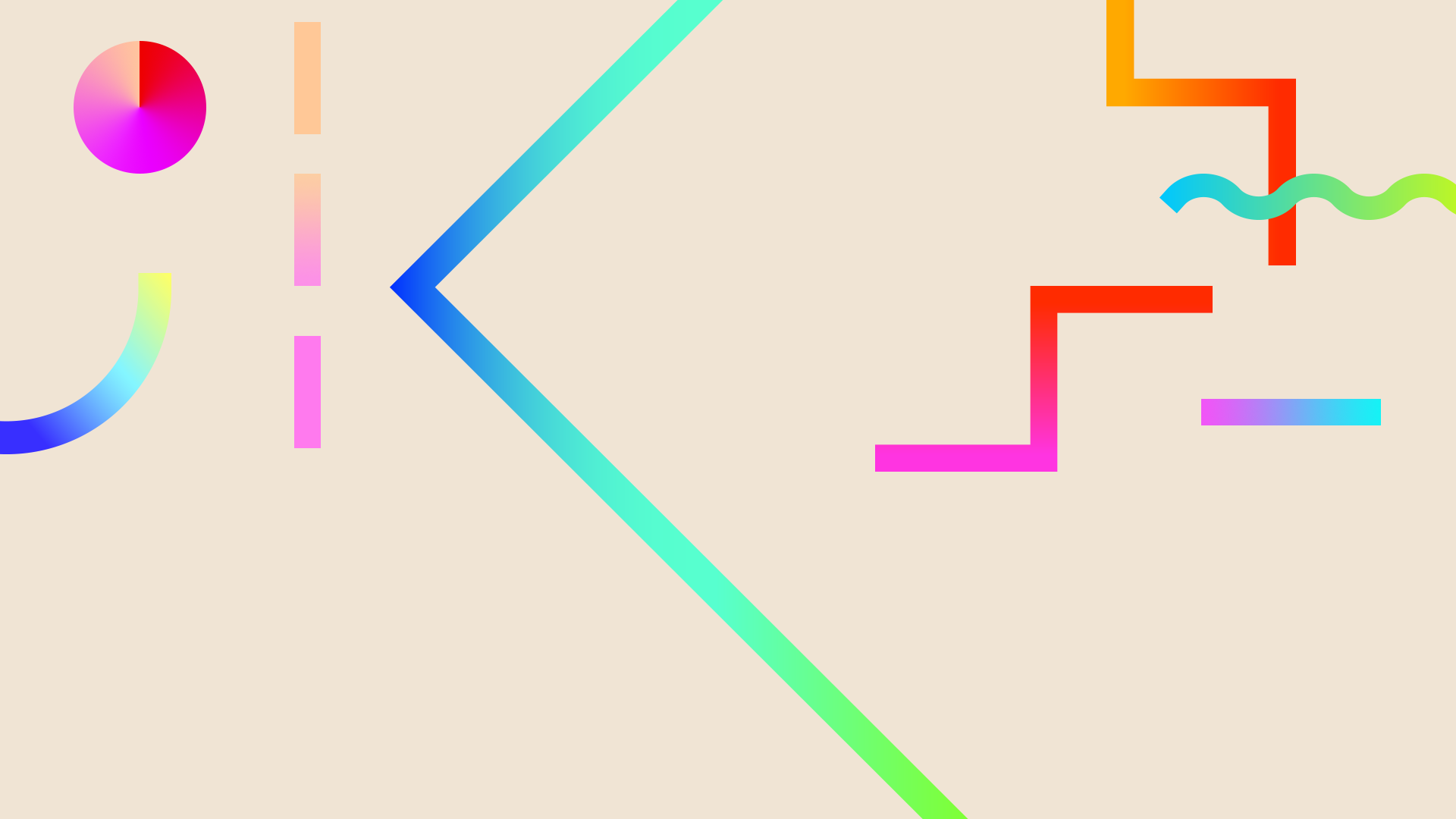所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール17
みなさん、こんにちは。 続きです。 どういう土地であれば、国に引き取ってもらえるのかだが、 これには一定の基準が設けられている。 たとえば建物が建っている土地、担保権などの権利が設定されている土地、 特定有害物質によって汚染されている土地などの条件に該当する土地は、...
所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール16
みなさん、こんにちは。 続きです。 「親と離れ、大都市圏で生活している子供は、親から実家の土地の相続を受けたとしても、 そこに戻って生活するとは限りません。 そのようなケースでは、実家の土地が所有者不明土地予備軍になりがちです。...
所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール15
みなさん、こんにちは。 続きです。 「相続土地国庫帰属制度」という選択肢が誕生 従来、相続した不動産を処分するに際しては、 ①不動産市場で売却する ②相続放棄する という2つの手段があった。これに加えて、2023 年4月27日に施行される 「相続土地国庫帰属制度」...
所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール14
みなさん、こんにちは。 続きです。 とはいえ、3年あるいは2年が経過した時点で即、過料を科されるわけではない。 「この期間が過ぎても登記がされていない場合は、 まず相続人に対して書面で催告します。 この時点で申請していただければ裁判所への過料通知はしない予定」とのことだ。...
所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール13
みなさん、こんにちは。 続きです。 なお、相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、 相続登記をしていない場合は改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。 また、住所等の変更登記についても、改正法の施行日から2年以内に行わなければならないこ...
所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール12
みなさん、こんにちは。 続きです。 具体的には、相続登記の申請の義務化は、相続によって不動産を取得した相続人は、 その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、 正当な理由がないのに義務に違反した場合は、...
所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール11
みなさん、こんにちは。 相続登記や住所等の変更登記の申請が義務化 この問題が全国規模で深刻化する前に、 所有者不明土地の拡大を防止することを目的にして行われたのが、 「民法等の一部を改正する法律」ならびに 「相続 等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の...
所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール10
みなさん、こんにちは。 続きです。 また、2020年度に国土交通省が行った調査結果によると、 全国における所有者不明土地の割合は24%であり、 そのうち63%が相続登記の未了によるもの、 33%が住所変更登記の未了によるものだ。 ...
所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール9
みなさん、こんにちは。 続きです。 所有者不明土地はさらに増えていく見込み そうした所有者不明土地は日本にどのくらいあるのだろうか。 法務省が2017年6月に公表した「不動産登記簿における相続登記未了土地調査」の結果がある。...
所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール8
みなさん、こんにちは。 続きです。 3つ目の問題は「土地取引の停滞」だ。 土地の所有者がわからない状態で、その土地を勝手に売買することはできないし、 元の所有者に無断で建物を建てるわけにもいかない。 当然、所有者が誰なのかをたどるにしても、行方不明になっている所有者を探すに...